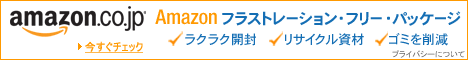亀戸天神社


東京都江東区にある「亀戸天神社」に行ってきました。
「亀戸天神社」は、学問の神様・菅原道真公を祀る神社 ( 天満宮 ) です。
この神社は、江戸時代の寛文元年 ( 1661年 ) 九州の太宰府天満宮から来た神官
「菅原大鳥居信祐 ( 菅原道真の末裔 )」が、道真に縁のある飛梅の木で彫った天神像
( 菅原道真の像 ) をこの地に祭ったことから始まりました。
その翌年の寛文2年 ( 1661年 ) には太宰府天満宮に倣って「社殿、回廊、心字池、
太鼓橋」などが造営され、それによって正式に東国天満宮の宗社となりました。
亀戸天神社は、その昔から「梅と藤」で有名なところで、それらが咲き誇る様子は、
江戸の浮世絵師・歌川広重の「名所江戸百景」にも描かれています。
もちろん現在も「梅と藤」の素晴らしさは健在で、それぞれ見頃の時期になると
「梅まつり」「藤まつり」が催され、たくさんの観客で賑わっています。
その他に有名なところとしては、
「うそ替え神事」「菊まつり」「五歳菅公像」「神牛」などがあります。
( 詳細は割愛。詳しくは 亀戸天神社のサイト でチェックしてね。)
なお、「うそ替え神事」の「うそ」とは、スズメ科の鳥「鷽 ( ウソ )」のことで、
亀戸天神社では「幸運を招く鳥」として扱われています。
このように様々な由緒ある亀戸天神社ではありますが、昭和20年 ( 1945年 )の東京大空襲で全焼してしまったため当時の建物は残っておらず、現在は「太鼓橋と社殿のみ」が再建されています。


今回訪問した「亀戸天神社」は、ウチの事務所の近所にあります。
ということで、花の見頃時期にはよく写真を撮りに出かけています。
そんな私から見た「亀戸天神社」の感想はといいますと、
-
・ 梅と藤が素晴らしい。
特に「太鼓橋」の上から眺める「藤色に染まった境内」は最高。 -
・ 境内が割と狭い。
なので、イベント時期 ( 特に「藤まつり」) の時の人口密度は強烈。 -
・ 最寄り駅から遠い。
徒歩で訪問される方は要注意。結構歩きます。
といった感じです。
ところで、さっき「花の見頃時期にはよく写真を撮りに出かける」と書きましたが、
その際は決まって平日訪問です。
その時期の休日は人がわんさかいて、じっくり撮影することなんて無理だからです。
混雑の中での写真撮影は他の訪問客のみなさんの邪魔になりますからね。
ちなみにイベント時期の休日は、他人のことはお構いなしの写真愛好家たちが三脚持参で良いポジションを取ろうと頑張ってるんで境内が軽い混乱状態になったります。
ということで、混雑が嫌いな方やじっくり写真を撮りたいと思う方には休日の訪問はオススメしません。
「休日じゃないと訪問できない…」という方でしたら、早朝の訪問がオススメです。
あと、亀戸天神社を紹介するに当たって個人的に外せないのが、
江戸時代・文化二年 ( 1805年 ) 創業の和菓子屋「船橋屋」さんです。
「創業以来、くず餅ひと筋!」という船橋屋さんは、亀戸天神社のすぐ近所。
くず餅はもちろん、あんみつ等も美味しいので、こちらもオススメです。
さて、今回紹介した「亀戸天神社」。
とても由緒ある雰囲気の良い所ですので、
梅や藤といった花々や伝統行事に興味のある方は、是非訪問してみてください。
■ 関連リンク
- ※ 本ページに掲載されている記事、及び、画像の無断掲載・転用はご遠慮願います。
バックナンバー
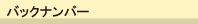
- ・千葉公園
- ・千葉ポートパーク
- ・八景島シーパラダイス
- ・港が見える丘公園
- ・山下公園
- ・鳥取砂丘
- ・大阪市立自然史博物館
- ・大阪城公園
- ・天保山公園
- ・茂林寺
- ・彦根城
- ・白川郷合掌造り集落
- ・高岡大仏
- ・立山黒部アルペンルート